おすすめお仕事特集FEATURE
こんにちは!センリョクエージェントの清水です。
「育児や介護と仕事の両立って本当にできるの…?」
そう感じている方は少なくないのではないでしょうか。
少子高齢化が進む現代において、育児や介護は私たちにとって身近な課題となっています。
そんな中で、仕事と家庭生活の両立をサポートするために重要な役割を果たすのが「育児・介護休業法」です。
今回は、前回に引き続き改正のポイントについて解説していきます!
育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、
正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
その名の通り、育児や家族の介護を行う労働者が、休業や短時間勤務などの制度を利用することで、仕事と家庭生活を両立できるよう支援するための法律です。
2022年の育児・介護休業法改正ポイント
2022年の改正では、主に男性の育児休業取得を促進し、育児と仕事の両立をより柔軟にすることを目的としています。
1.雇用環境の整備と個別周知・意向確認の義務化
企業業は、妊娠・出産の申し出をした労働者(男女問わず)に対し、育児休業制度について個別に知らせ、休業の意向を確認することが義務付けられました。
これにより、労働者が制度を知る機会が増え、安心して利用できる環境が整えられます。
2.有期雇用労働者の取得要件緩和
有期雇用労働者が育児休業や介護休業を取得するための要件が緩和され、より多くの人が制度を利用できるようになりました。
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる新しい制度が創設されました。
これは従来の育児休業とは別に取得でき、分割して2回まで利用可能です。
男性版産休とも呼ばれ、男性が育児の初期段階から積極的に関われるようになります。
4.育児休業の分割取得
これまでの育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、この改正により、子が1歳になるまでの間に分割して2回まで取得できるようになりました。
これにより、夫婦が交代で育児を行うなど、多様な働き方が可能になります。
参考:【2022年度版】育児介護休業法の改正内容と押さえておきたいポイント(YouTube)|厚生労働省
2025年の育児・介護休業法改正ポイント
2025年の改正の背景には、少子高齢化のさらなる進展と、それに伴う「2025年問題」があります。
国民の5人に1人が後期高齢者となる社会において、介護離職を防ぎ、労働力を確保することは喫緊の課題です。
また、共働き世帯の増加や多様な働き方へのニーズの高まりも、柔軟な育児支援制度が求められる理由の一つです。
今回の改正は、こうした社会の変化に対応し、誰もが安心して働き続けられる社会を目指すための重要な一歩と言えます。
育児に関する主な改正ポイント
1.子の看護休暇の拡充
これまでの「子の看護休暇」は、対象が「小学校就学前」の子どもでしたが、対象が「小学校第3学年修了まで」に拡大されます。
さらに取得できる理由も拡充されました。
これまでの「病気・けが、予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」も取得理由として認められます。
これにより、多くの親が直面する「小1の壁」と呼ばれる問題(子どもの小学校入学を機に、仕事と育児の両立が難しくなること)の解消にも繋がることが期待されています。
2.残業免除の対象拡大
これまで、残業(所定外労働)の制限を請求できるのは、「3歳に満たない子ども」を養育する労働者でしたが、対象が「小学校就学前の子ども」まで拡大されます。
これにより、子育て中の労働者は、子どもの保育園の迎えや体調不良に備えるため、残業の免除を会社に請求できるようになります。
3.柔軟な働き方の実現
3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、会社は以下のうち2つ以上の措置を講じることが義務化されます。
- 始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制など)
- テレワーク(月10日以上)
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与(年10日以上)
これにより、子どもが3歳を過ぎた後も、個々の状況に合わせて柔軟な働き方を選択できるようになります。
4.育児休業取得状況の公表義務拡大
男性の育児休業取得をさらに促進するため、育児休業の取得状況の公表義務の対象が、従業員数1,000人超の企業から300人超の企業へと拡大されます。
介護の関する主な改正ポイント
1.介護休暇の取得要件緩和
これまで、労使協定により「継続雇用期間6ヶ月未満」の労働者を介護休暇の対象から除外することが可能でした。
今回の改正により、この除外規定が撤廃されます。
これにより、入社して間もない労働者も、いざという時に介護休暇を取得できるようになり、より安心して働くことができるようになります。
2.仕事と介護の両立支援
介護離職を防ぐため、以下の措置が企業に義務付けられます。
- 個別の周知・意向確認の義務化: 介護に直面した従業員に対し、両立支援制度について個別に周知し、利用の意向を確認することが義務化されます。
- 雇用環境整備の義務化: 介護に直面する前の段階(例えば40歳など)で、研修や相談窓口の設置などを行い、従業員が事前に情報にアクセスし、安心して相談できる環境を整えることが義務付けられます。
企業にとっても、従業員の仕事と家庭の両立を支援することは、優秀な人材の確保や定着に繋がります。
私たち一人ひとりも、これらの改正内容を正しく理解し、必要に応じて積極的に活用することで、より豊かなキャリアと生活を築いていきましょう。
有期雇用労働者は対象になる?
派遣社員を含め、有期雇用労働者は育児・介護休業法の対象になるのでしょうか?
2022年の改正により有期雇用労働者の取得要件が緩和されたため、
以前の「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が撤廃されました。
そのため、現在は有期雇用労働者も、以下の要件を満たせば育児休業や介護休業を取得できます。
育児休業の場合
子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと
育児休業を1歳6か月まで延長する際は、子が2歳に達する日まで、というように、休業する期間まで契約が満了しないことが条件となります。
介護休業の場合
介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと
ただし、日雇い労働者は対象外です。
また、労使協定が締結されている場合は、以下の要件に該当する有期雇用労働者は対象外となることがあります。
- 育児休業の申出があった日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
要するに、2022年の改正以降、有期雇用労働者でも、雇用契約の期間が育児や介護のための休業期間を超えて続くことが明らかであれば、育児休業や介護休業を取得できる可能性が非常に高くなっています。
もしご自身の状況について不安な点がある場合は、会社の就業規則を確認するか、人事担当者や労働局に相談してみましょう。
時代に合わせて改正が繰り返されている
育児・介護休業法
育児・介護休業法は時代背景に合わせて改正を繰り返してきました。
直近ですと2022年と2025年に改正が行われました。
加速する少子高齢化社会と労働人口減少に対応していくため、
わたしたちが介護や育児と仕事を両立でき、働きやすい環境づくりのために重要な法律です。
わたしたち自身もしっかりと理解し、制度を活用できるようにしていきましょう!
\ あなたに寄り添ってお仕事を紹介します! /
自分一人では就職活動や転職活動がなかなかうまくいかないという方にはセンリョクエージェントの担当が寄り添います!
みなさんのご希望に合わせた幅広いお仕事をご提案、転職活動のサポート、お仕事スタート後のフォローまで一人の担当が徹底してサポートいたします。
未経験スタートOKのお仕事も多数!
お仕事探しをされている方はぜひ一度検討してみませんか?
web登録はこちらから
<対応エリア>
東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/栃木県/茨城県/群馬県/山梨県
静岡県/愛知県/大阪府/京都府/滋賀県/奈良県/兵庫県
<対応職種>
製造/物流/事務/研究開発/軽作業など多数
▷ 新卒・中途採用も実施中!
「スタッフを大切にする会社」の一員として働きませんか?
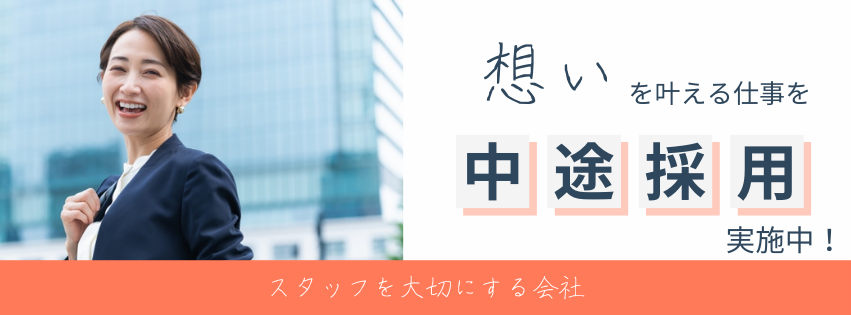
この記事の執筆者:センリョクエージェント 清水
センリョクエージェントに新卒として入社後、人材派遣の営業担当として地域の企業や求職者をサポート。
その後新卒採用や研修を担当し、現在は中途採用を担当しながら広報として自社の知名度アップのために試行錯誤中です。
今年の目標は「おいしいランチに巡り合うこと!」

